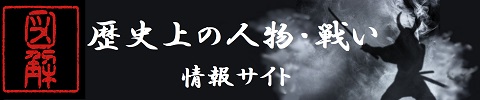|
全 般 |
北海道 東北 |
関 東 |
中 部 |
近 畿 |
中国 四国 |
九州 沖縄 |
| 大坂の陣 | 鳥羽伏見の戦い | 本能寺の変 | 姉川の戦い | 賤ヶ岳の戦い | 応仁の乱 |
あなたは
どっち派?
36票 vs 31票
- 仲良くしろお市の取り合い
光秀以来の昇進者
信長に一番信頼されていたのはわしじゃ - 猿
刃向かうつもりか
賤ヶ岳の戦い
先日まとめた『姉川の戦い』の最初で「琵琶湖の東が一大決戦の場になっている」という事を書きました。『賤ヶ岳の戦い』も同じ滋賀県長浜市なので、その賤ヶ岳も当然、琵琶湖の東にあるものだと…。
いや、違うじゃないですか!浅井氏小谷城のすぐそばかと予想してたんですが、実際には琵琶湖北岸なんですね(小谷城から10kmほど北西に賤ヶ岳を見つけました)。余呉湖周辺(この湖も知らなかったのですが…)なので琵琶湖の東とは少しズレてますが、まぁ大目に見てくださいませ。
私自身の今後の為にも、この付近の位置関係を地図に表示しておきます。何度か道を通過しただけ(関ヶ原までは行きますがそこから京都方面に行っちゃう時が多かったので…)では、案外土地勘って身に付かないものなんですね。反省ついでに、近々現地史跡見学しに出掛けてみようとも思っています。
※追記:後日、リフトで賤ヶ岳に登ってきました。
彦根城関ヶ原古戦場長浜城姉川古戦場小谷城賤ヶ岳
就職したてで愛知県江南市に住んでた頃、車で西に行くには大垣市→関ヶ原が常に通る経路でしたね(新幹線などの鉄道もそうです)。当時の名古屋→鈴鹿越えは、今でこそ高速道路が開通していますが、まだそんなに主流ではなかったです。徳川家康も必死に伊賀越えしましたし、戦国時代もやはり中山道(関ヶ原ルート)がメインだったんでしょう。こうして地図であらためて見ると、この地域が京都とを結ぶ水運・陸上交通の重要拠点であった事が再確認できます。
信長家臣
今回の『賤ヶ岳の戦い』の両者『柴田勝家』『羽柴秀吉』は、共に『織田信長』の家臣です。羽柴秀吉は、後の天下人『豊臣秀吉』。この頃の名字はまだ『羽柴』なんですが、実は対戦相手の『柴田』(と、信長重臣『丹羽』)から一字貰い受けて付けたものです。
勝家は、若いうちから信長の父に仕えてきた織田家の重鎮。一方、秀吉は農民出身で、信長の草履取り(主人の為に懐で温めていたエピソードが有名)から出世していった叩き上げです。秀吉がめざましい活躍をして有力武将になっていたとはいえ、格の差は歴然。その憧れの対象からいただいた羽柴の姓を、自ら名乗り始めたのが35歳(一回り以上違う勝家は、50歳)と言われています。漢字の組み合わせ(『柴』が後ろでいいのか?)についても諸説ありますが、敢えて『羽』という名字の2文字目を選ぶ事で優劣をつけずお二人に配慮したと言われる話が「秀吉らしいなぁ」と思ったりしましたね(実話かどうかは、定かではないですよ)。

・四国地方……丹羽長秀
・北陸地方……柴田勝家
・中国地方……羽柴秀吉
・関東地方……滝川一益
・近畿地方……明智光秀
各方面軍がそれぞれの立場で奮闘しているそんな折、京都近辺で転戦していた『明智光秀』が主君にそむいて兵を挙げます。突如勃発した『本能寺の変』で、信長は討ち死に!
柴田勢・滝川勢よりいち早く行動した秀吉は『中国大返し』を成功させ、反逆者の光秀と山崎の地で対峙(丹羽勢の一部も合流)。天下分け目の天王山となるこの弔い合戦に勝利し、信長の後継者としての道を歩み始めるのでした。
清洲会議
信長と共に織田家当主の嫡男も本能寺の変で自刃していたので、主要なメンバーで今後の方針の話し合いが行われることになります。清洲城に集合した重臣は、筆頭家老『柴田勝家』、主君の仇を取った『羽柴秀吉』、その決戦に貢献した『丹羽長秀』『池田恒興』の4名。なお『滝川一益』は未だ帰路の途中であり、この会議には間に合いませんでした。

話を元に戻して…。織田家の跡継ぎをどうするかが要点となったこの会議で、勝家は信長三男信孝を推します(ちなみに、大将の器ではなかった信長次男信雄は後継者候補とはなりませんでした)。それに異を唱えた秀吉は、意外にも亡くなった信長長男(当主)の嫡男(信長の嫡孫)『三法師』を擁立。まだ3歳という若さではあるものの正統な直系の血筋です。相反する意見の決着は、やはり裏切り者を倒した秀吉の実績が大きく影響しました。(事前の根回しもあり)次席家老の丹羽は秀吉に賛同、同じく決戦の地に居た池田も合意します。
敵討ちの手柄を取れなかった勝家との信頼度は明確に入れ替わっており、続く領地再配分でも秀吉の思惑通りに事が進みます。実質的な石高も、そこで勝家を逆転し…。

対立
頭一つ抜きん出た秀吉は各方面を巻き込み地盤固めを…。身構える勝家もそれに対抗…。両者の間には緊張が走り、織田家重臣は二分されていきました。清洲会議で後継者となれなかった織田信孝は勝家に近付き、会議欠席となった滝川一益と共に秀吉への対立姿勢を取り始めます。
ところが、勝家のいる北陸は雪で行動が制限されるという弱点を持っていました。冬を迎える前、与力(柴田軍に所属して力を貸す武将)である『前田利家』を使者として和睦交渉に向かわせますが、秀吉と利家は共に切磋琢磨した戦友とも言える仲…(隣同士の頃から家族ぐるみで親しく付き合っています)。こんな調略のチャンスを秀吉が逃すはず無いですよね(これが後に『賤ヶ岳の戦い』の決定打となります)。

活気づく秀吉勢に対し、滝川一益が伊勢を拠点として挙兵。およそ7万の兵で押し寄せる秀吉軍と対峙する中、これまでの戦況に業を煮やした北陸の勝家が遂に動き出します。
勝家vs秀吉
3万の兵を率いて近江に布陣する勝家。伊勢で滝川の応戦をしていた秀吉は、約2万の兵を織田信雄に任せて残し、急ぎ近江へ(戦線はしばらく膠着状態)。二分されてしまったとはいえ、勝家に対抗する秀吉の兵力は5万!数で圧倒するも、今度は降伏したはずの織田信孝が再度挙兵し盛り返しをみせます。三方面(近江・美濃・伊勢)への対応を迫られ移動する秀吉、その留守を突く様に近江での戦闘『賤ヶ岳の戦い』は始まるのでした。


桑山重晴中川清秀高山右近羽柴秀長堀秀政木村隼人正木下一元佐久間盛政前田利家柴田勝政柴田勝家丹羽長秀羽柴秀吉
勝負を決定付けた前田利家は、心底迷ったでしょうね。大親友の秀吉からは「勝家軍として参陣しないわけにはいかないだろうから、せめて動かないでいてくれ」と頼まれていたそうです。ただ、勝家は若い頃から大変世話になっている先輩(浪人生活を送る事になった笄斬り事件の仲裁など)であり、見捨てるわけにもいきません。それでも秀吉を選んだのは「親父様なら許してくれるはず!」と思ったからに違いないはず…。実際、勝家が負けて撤退する途中、離脱した利家に叱る事無く「これまでの働きに感謝する」ことを伝えています(勝家のお人好し過ぎる面を感じるエピソードですね)。

越前に戻った勝家は、自分に付き添ってくれた妻『お市の方』と自害し、その一生を終えました。織田政権内での主導権争いを勝ち抜いた秀吉は、以降、天下統一へ向けて突き進んでいくのです。